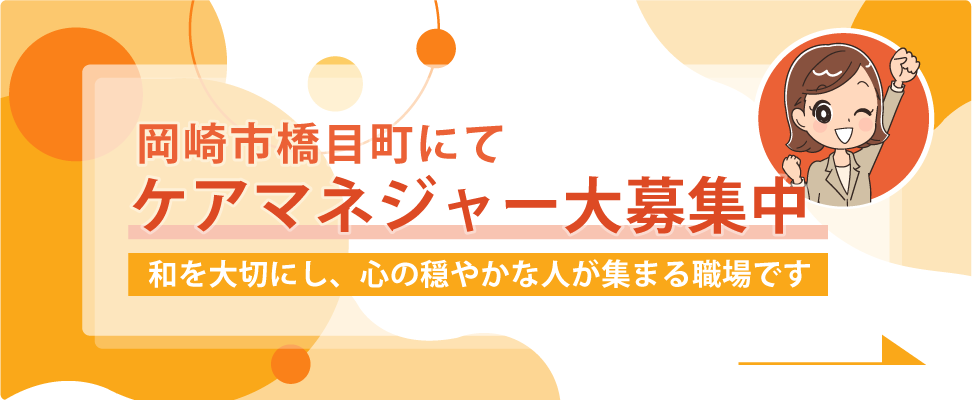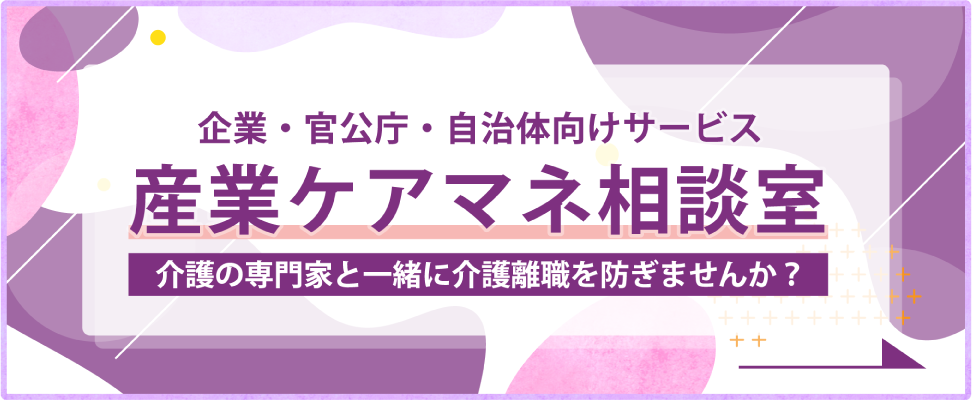岡崎市の療育支援体制について一般質問
今、9月の定例会の最中です
9月1日から定例会が始まり
一番最初の週には一般質問が行われました
私は今回の一般質問で
「障害児の療育」をテーマに取り上げました
今回はその内容についてお話ししたいと思います

療育とは何か
今回の一般質問では
障害児の療育支援体制について質問をしました
私はもともと高齢者介護の福祉が専門ですが
障害福祉も大切な分野です
特に今回は子どもの療育支援について
焦点を当てました
療育という言葉を聞いたことはあっても
実際にどういうものなのか
分からない方も多いと思います
療育とは、障害のある子どもに対して
成長の過程でリハビリや教育
医療を適切な時期に行う支援です
発達障害や身体障害を持つ子どもは
それぞれ異なる課題を抱えています
言葉、運動、空間認識など
自分で表現しにくい課題を専門家が見極め
必要な支援を施すのが療育なのです
療育は年々「早期発見・早期開始」が
重要だと言われています
岡崎市でも1歳半健診や3歳児健診など
保健師さんとの面談をきっかけに
療育が始まることもあれば
幼稚園での先生からの指摘をきっかけに
気づかれるような親御さんもいらっしゃいます
早期発見は大切である一方で難しさもあり
親御さん自身が気づけなかったり
受け入れにくいということもあるそうです
また療育を受けたからといって
すぐに効果が現れるとは限らず
もしかしたら
一生を通して寄り添う必要があるかもしれない
そうしたことからも
特に就学前のお子さんにとっては
親子で療育に取り組むことが重要なんですね
急増する予算と課題
私自身も言葉では聞いたことがありますし
周りにもそういうお子さんがいることを
知ってはいましたが
今回一般質問をするにあたり
「岡崎市では今どういう状況なのか」
「課題はどこにあるのか」という視点で調べました
障害児福祉サービスの中にある
「障害児通所給付費」
いわゆる放課後デイや療育通所に使われる予算は
近年本当にすごい勢いで急増しています
令和3年度は20億円
令和4年度は23億円
令和5年度は28億円
令和6年度は33億円
わずか数年で20億円から33億円へと
急増しているのです
少子化で子どもの数は減っているのに
療育の予算は膨れ続けているのはなぜなのか
ここに大きな課題があると考え質問しました
療育が必要な子どもに
適切な時期に支援を行うことは絶対に必要です
これは譲れない視点です
ただ、療育を受けることで小学校入学後には
すでに障害児サービスを受ける
必要がなくなっているお子さんもいるはずです
その一方で、障害サービスを利用するための
「受給者証」が交付されると
その後に「適正なサービス利用状況であるのか」
という評価が十分にされていないのではないか
これが今回の一般質問の論点でした
部署をまたぐ仕組みと責任の所在
岡崎市には
こども発達センター「すくも」という施設があり
相談から検査、通所支援までが行われています
ただ実際には
こども発達相談センターはこども部
こども発達医療センターは市民病院
通所支援は福祉部と
複数の部署が関わります
さらに小学校に進めば教育委員会も加わります
一つの施設の中で
多職種の連携が実現していることは
本当に素晴らしい仕組みだと思います
しかし、支援を利用するために必要な
受給者証を発行している福祉部は
「どれくらい利用されたか」までは把握していても
利用を終了した理由についての分析や評価は
行っていない状況というのが
今のこの制度の現実なんですよね
それぞれの部署は一生懸命熱心に取り組んでいるんです
そのことは本当に評価しています
ただ、成長の過程を連続して支援する中で
責任の所在が
曖昧になっているのではないかと感じました
ここが課題であり
これからしっかりと取り組んでいかなくては
いけないところじゃないですかという
今回の質問に対して
明確な回答は得られませんでした
国はこども家庭庁という一つの所管で
施策を進めていますが
自治体では複数部署が関わらざるを得ない
この仕組みそのものに矛盾があり
その結果、予算が膨張し続けています
予算が増え続ける理由は分析されていると
言われていますが
本当に十分な分析なのか疑問が残ります
持続可能な療育支援体制を維持できるのか
ここを真剣に考えなければいけません


現場の声と私の学び
今回の一般質問に向けて、すくもを訪問し
職員や親御さんにインタビューを行いました
3歳の男の子の親御さん
大人になった元療育経験者のお母様からも
直接お話を伺いました
現場の感覚として
「療育を必要とする子どもは確実に増えている」
そう、先生方はおっしゃっています
子どもの数が減っているのに
支援を必要とする子の割合は増えている
これは
「グレーゾーンのお子さんも早期に療育を始めよう」
という世の中の流れもありますが
それだけでは説明できない
何か大きな要因があるのではないか
社会全体で起きている変化も視野に入れ
考えていく必要があるのではないかと
今回の一般質問で改めて感じました
おわりに
今回は「障害児の早期療育支援」について
一般質問をした内容をお話ししました
私は岡崎市議会議員として
岡崎市を例にお話ししましたが
この傾向は他の自治体でも共通していると思います
地域の体制を見直し
疑問があれば声を上げていくことが
よりよい療育支援体制に
つながるのではないかと感じています