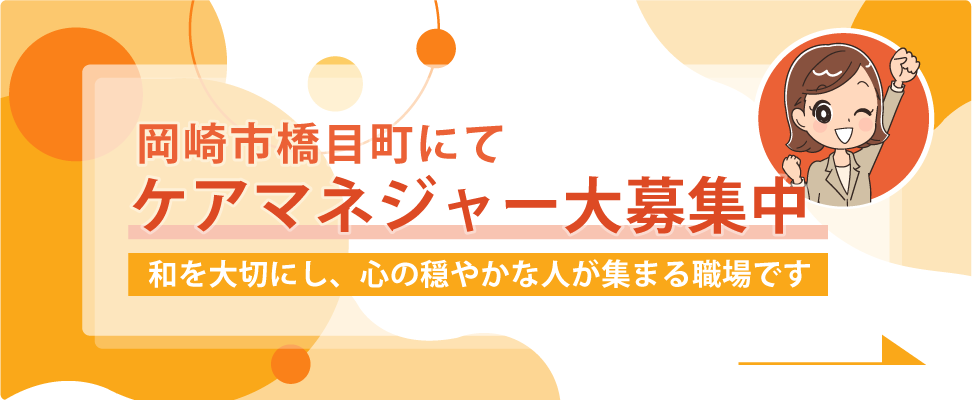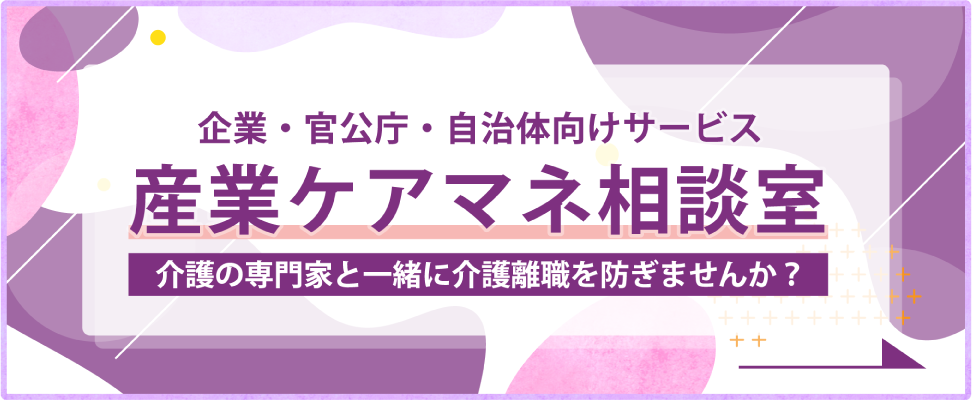おにぎり協会を視察
先日の視察で「おにぎり協会」を訪れました
そう言うと「おにぎりを食べに行ったの?」
そう思われるかもしれませんが、そうではないのです
おにぎりというコンテンツを活用した
自治体や企業との
さまざまな取り組みの事例を学びに訪れたのです
まちづくりや人材の発掘
地域活性化といった
幅広い可能性がある取り組みだったので
今日はその内容をご紹介します
大塚の行列店「ぼんご」
視察初日は、まず東京都内の「大塚駅」で下車
有名な老舗おにぎり屋さん「ぼんご」へ向かいました
創業から60年ほどになるお店で
決して広い店内ではないのですが
イートインは10席ほど
シンプルな、おにぎりとお味噌汁
そして素朴なお漬物というメニュー構成です
この「ぼんご」を目指して
平日の11時ごろにもかかわらず
お店の前には20人ほどの行列が
それでも「今日は少ない方だよ」と
言われるほどの人気ぶりで
日本人だけでなく外国人の方も多く並んでいました
向かいには星野リゾートのホテルがあり
そこに宿泊しているお客さんが
連日通うということも多いようです
お店では、70代くらいの素敵なおかみさんと
「おにぎり」について
いろいろとディスカッションさせていただきました
この「ぼんご」は、今回の視察のメインでもある
「おにぎり協会」に所属している店舗の一つなんです
「おにぎり協会」という仕掛けと仕組み
おにぎり協会は
2014年に中村さんという方が立ち上げた団体です
どんなビジネスをしているかというと
自治体や企業を巻き込みながら
「おにぎりサミット」というイベントを
定期的に開催していて
加盟団体がブースを出したり
自慢のおにぎりを発表・試食できる場を作ったり
団体同士がコラボして
新しい企画を展開するようなことをしています
おにぎりはあまりに身近すぎて
その可能性や価値に気づかれていない部分も
あるんじゃないかなと思うんですが
実は海外ではビジネスとして成功している例もあります
たとえばアメリカ・シカゴでは
「Onigiri KORORIN」というブランドが
40店舗に卸していて
1個8ドル(約1200円)ほどで販売されているそうです
アニメ文化の影響もあって
おにぎりは“食べてみたい和食”として
世界でも注目されているそうなのです
おにぎり×地域資源のコラボの可能性
この協会の取り組みで面白いと感じたのは
防災食との連携です
たとえば、大西食品や亀田製菓の子会社が開発した
「お湯を入れるだけでおにぎりになる」
パウチ商品などが紹介され
自治体に向けて導入の提案もされています
また、自治体は年間40万円で
おにぎり協会に参加することができ
都心の一等地である東京ミッドタウン八重洲での
「おにぎりサミット」で
自治体ブースを出すことが可能になるそうです
たとえば岡崎市なら
特産品である八丁味噌を使ったおにぎりを開発し
そこでPRすることもできるわけです
自治体のシティプロモーションとして考えると
40万円という費用感で、その価格以上といえる
これだけの露出や企画に参加できるのは
かなり魅力的だと感じました
さらに、おにぎり協会は場を提供するだけでなく
商品開発にもコンサル的に関わってくれます
「こんな具材との組み合わせはどうか」
「こういう部署に相談してみるといいかも」といった
具体的なアドバイスをもらえるため
自治体単独では思いつかないような
アイデアも生まれやすいんですね
自治体同士や自治体と企業のコラボも
展開しやすいんじゃないかと感じました
たとえば、あのコカ・コーラも
このおにぎり協会に参加しています
コカ・コーラ製品「綾鷹」とのタイアップを行っている
おにぎり屋さんもあるそうで
販売促進プロモーション効果は大きいとのことでした
岡崎でも仕掛けられるかもしれない
おにぎりって、誰でも知っていて
しかも地域の食材と掛け合わせやすいからこそ
小さなおにぎり屋さんから自治体、企業まで
いろんな形で関わることができるんですよね
おにぎり協会への参加は25自治体までと決まっていて
すでに13自治体が参加しています
つまり、あと12自治体で締め切りになるとのこと
岡崎市もぜひ、その中に入っておきたいなと思いました
たとえば八丁味噌を使ったコラボおにぎりで参加し
岡崎の味を知ってもらうきっかけにできたら
面白いなあと
大学とのコラボレーションも視野に入っているそうで
今後さらに活動は広がっていきそうです
おにぎり協会の活動を見て改めて
「誰もが知るコンテンツを
どうやってまちづくりのツールに変えるか」
という視点の大切さを感じました
日常にある何気ないものが
工夫とつながりで地域を動かす力になる
そんな視点を、今回の視察で教えてもらいました