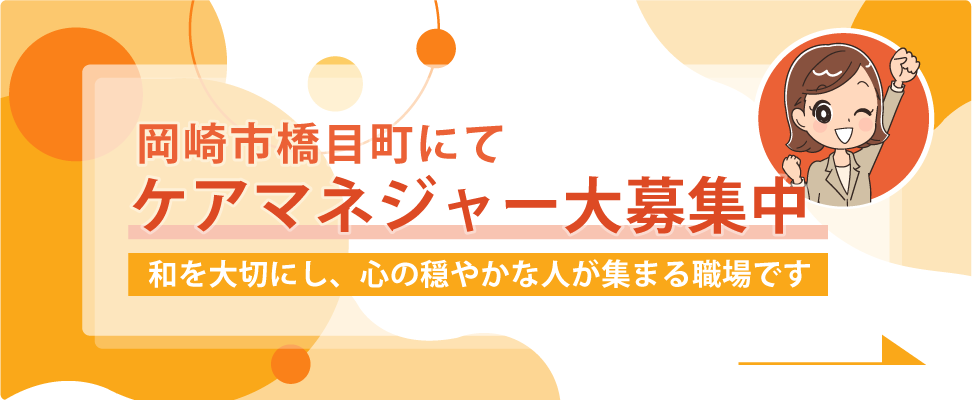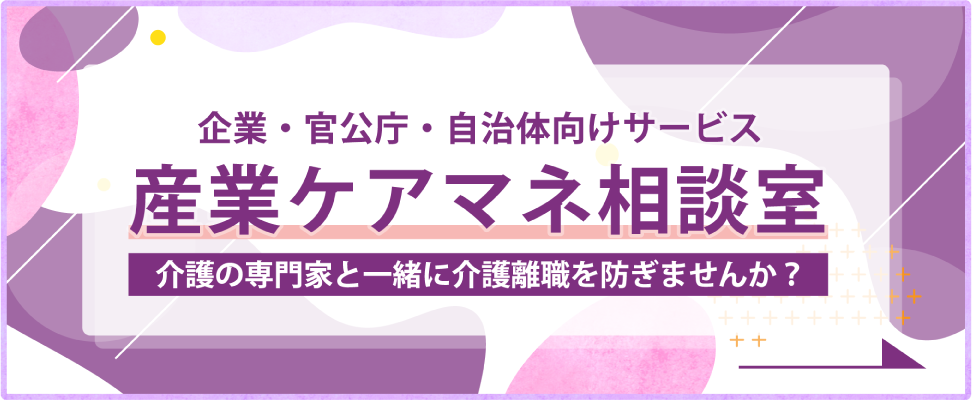産業ケアマネの必要性を届けるために〜高齢者住宅新聞3月26日号より〜
「高齢者住宅新聞」という
ちょっとニッチな業界紙ですが
実は、定期的にコラムを掲載させてもらっています
その3月26日号に、私の最新のコラムが掲載されました
「産業ケアマネコンサルタント養成講座」立ち上げのきっかけ
今回はコラムの内容から、私が主催している
「産業ケアマネコンサルタント養成講座」について
ご紹介したいと思います
まず、産業ケアマネというのは
「ケアマネージャーを紡ぐ会」が作った資格です
2020年から年2回の試験がスタートし
今では合格者は全国で1000名を超えました
そして「産業ケアマネコンサルタント養成講座」は
この産業ケアマネの資格を取ったけれど
実際に企業と顧問契約を結べずに
悩んでいる方に向けて立ち上げたもの
ケアマネって、基本的に営業しなくても
地域包括支援センターから紹介が来る仕事なので
いきなり企業と取引しようにも
戸惑う人がほとんどなんです
そんな現状を変えるために
産業ケアマネとしてどうやって企業と関わるかを
学べる講座を作りました
産業ケアマネである進 絵美さんと山崎 理央さんを
講師にお迎えし、講座を開催しています
5月からは5期生もスタート
延べ100人の講座生が卒業することになります
資格を活かして活躍する
「高齢者住宅新聞」のコラムでは
養成講座の卒業生の中で活躍されている方を
ピックアップして紹介しています
今回は第2期の卒業生、服部陽子さんを紹介しています
服部さんは、東京にある
「介護屋みらい」という居宅介護支援事業所に
勤めていらっしゃいます
この事業所では、介護保険サービスだけでなく
介護保険外のサービスとして
産業ケアマネの取り組みを行っていて
すでに四つの法人と顧問契約を結んでいるんです
この「介護屋みらい」は
ケアマネージャーを紡ぐ会の前会長・宮崎さんが
経営されていたところでもあり
現在2名の産業ケアマネが活躍中です
本音に寄り添うから、信頼される
服部さんがすごいのは
単に資格を持っているというだけでなく
企業に対して自分で考えてプレゼンし
社長さんと直接話して契約に至っているところ
たとえ知り合いでも
必要性がなければサービスは入れてもらえません
社長さんにとっては
会社のお金をどう使うかが常に判断の軸なんですよね
そんな中で服部さんは
従業員さんと経営者さん、両方の「本音」に
寄り添っているんです
国の制度である「介護休暇」はあっても
その期間収入が減ってしまうという現実
そのため、家族の介護が始まっても
従業員さんはなるべく休まずに働きたい
一方で、経営者としてもできるだけ休んでほしくない
この両者の気持ちを尊重して間に立ち
どうすれば介護と仕事のバランスがとれるのか
柔軟な提案をしていく
それが産業ケアマネの仕事なんですよね
「答えは相談者の中にある」
服部さんがコンサルをする際に大切にしているのが
「答えは相談者の中にある」という考え方
人って説得されるより
自分で納得して選んだ方が行動に移しやすいですよね
だからこそ
彼女は必ず三つ以上の提案を用意してその中から
相談者自身に選んでもらうようにしているそうです
そうすることで、行動が受け身ではなく
自分で選んだという意識に変わります
産業ケアマネは
その選択を後押しする存在でもあるのです
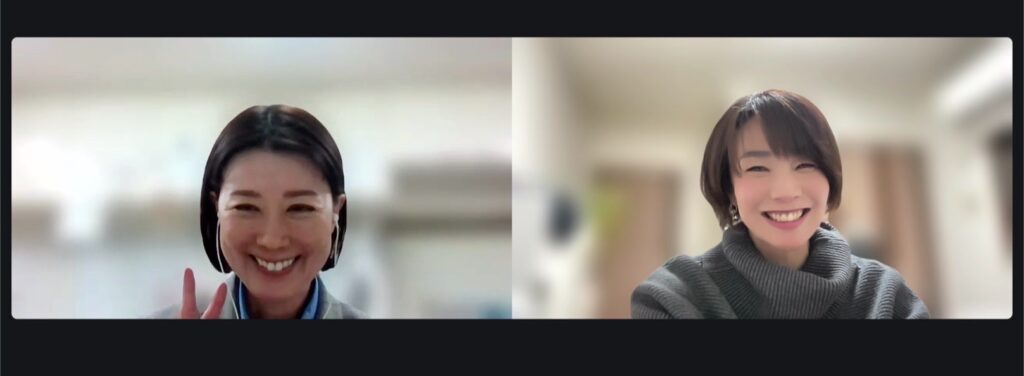
産業ケアマネの価値を、もっと知ってほしい
今回のコラムでは
産業ケアマネが企業の中で
どのように活躍しているのか
服部さんの実例を通してご紹介しました
産業ケアマネは、これからの時代に本当に必要な存在です
なぜなら、今後すべての事業所において
従業員の介護に関する対応が求められてくるから
そのとき、企業・従業員双方の本音を汲み取り
制度の活用や働き方の提案をしていく
それができるのが、産業ケアマネという存在なんです
私たちはただ制度を伝えるだけでなく
人の想いに寄り添い、企業に寄り添いながら
介護と仕事の両立を支えていきます
そんな存在が
もっと企業の中で当たり前になる未来を目指して
活動を続けています